たなか
BLOG
ユーザーに伝わるWeb文章とは?UXライティングで快適なウェブサイト作り
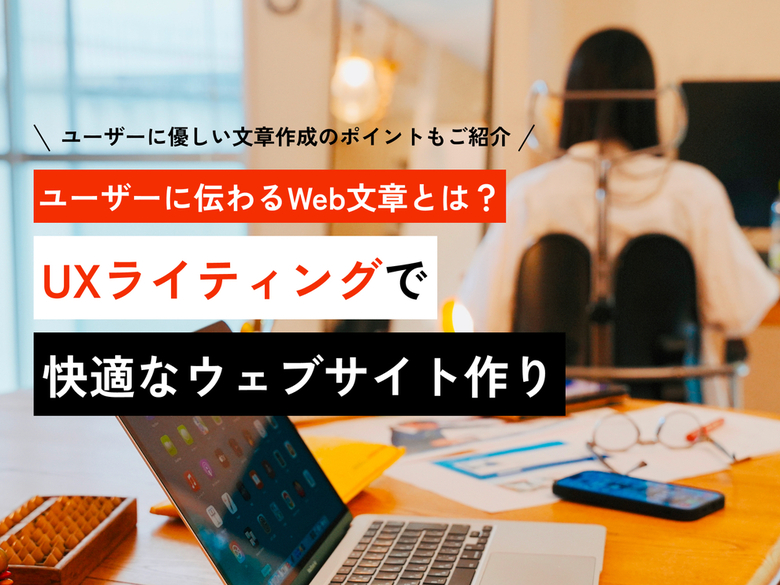
ホームページは、デザインや機能面にばかり目が行きがちです。しかし、サイトを訪れたユーザーの行動を後押しするものはそれだけではありません。もうひとつ大きなポイントとなるのが、「文章」の役割です。
わかりやすい言葉があることで、ユーザーは「何を見ればいいか」「次に何をすればいいか」を迷わず理解でき、ストレスなくサイトを利用できます。
わかりやすい言葉があることで、ユーザーは「何を見ればいいか」「次に何をすればいいか」を迷わず理解でき、ストレスなくサイトを利用できます。
この記事では、そんな「快適なウェブサイト作り」に欠かせない考え方として近年注目されている「UXライティング」についてご紹介します。わかりやすい言葉がどのようにサイトの成果を高め、お客様との信頼につながるのか。その基本と、すぐに使える実践のヒントをお伝えします。
UXライティングとは?
UXライティングとは、ウェブサイトを訪れた訪問者のユーザー体験(User Experience)を高める文章術のこと。一言で言えば「ストレスなく情報が適切に伝わるライティング術」です。
◾️UXライティングの目的
UXライティングの目的はユーザーがスムーズに目的を達成できるよう、言葉でサポートすることです。近年は、ウェブ上で完結できることが増えた分、サイトの機能や操作も複雑になってきています。UXライティングの目的は、ユーザーがウェブサイト内で次に取るべき行動に迷う事なく、スムーズに目的を達成できるようサポートすること。いわば「親切に案内してくれる接客スタッフ」のような存在なのです。
◾️コピーライティングとの違い
「文章術」「ライティング」という言葉を聞くと「コピーライティング」を思い浮かべるかもしれませんが、UXライティングとコピーライティングには明確な違いがあります。
コピーライティングは「印象に残すこと」「心を動かすこと」を目的としますが、UXライティングは「自然で平易、簡潔であること」そして「ユーザーの考える負担を減らすこと」が重要です。
コピーライティングは「印象に残すこと」「心を動かすこと」を目的としますが、UXライティングは「自然で平易、簡潔であること」そして「ユーザーの考える負担を減らすこと」が重要です。
ユーザーに意識されることなく操作の流れに自然と溶け込み、直感的に「次に何をすればよいか」を理解できる状態に導く。これが優れたUXライティングの特徴と言えるでしょう。
「翻訳・解析しやすい」文章の重要性
グローバル化とAI技術の進化が進む今、UXライティングは「人にとってわかりやすい」だけでなく、「AIや検索エンジンにも正しく伝わる」文章としての重要性が高まっています。
◾️なぜ「翻訳のしやすさ」が重要なのか
日本語は機械翻訳が特に難しい言語とされています。
主語が省略されやすく、文脈によって意味が変わる表現も多いうえに、接続詞や助詞の文中での使い方も解釈が分かれやすく、こうした特徴が誤訳の原因になりがちです。
主語が省略されやすく、文脈によって意味が変わる表現も多いうえに、接続詞や助詞の文中での使い方も解釈が分かれやすく、こうした特徴が誤訳の原因になりがちです。
例えば、「A社のBという製品に関する企画書」という文章があった場合「A社が作成した”Bという製品に関する企画書”」とも「”A社が開発したBという製品”に関する企画書」とも読めてしまいます。
こうした文章の曖昧さは、多言語化する際の誤訳やAIのミスリーディングに繋がる可能性があります。このような曖昧さを避けるためには、誰が読んでも一つの意味にしか取れない、シンプルで明確な表現を心がけることが重要です。
◾️AI時代に求められる文章とは
わかりやすい文章とは、人間だけでなく、検索エンジンやAIにとっても「理解しやすい」ものです。ページ内容が正しく読み取られれば、Google検索でも適切に評価され、検索順位の向上が期待できます。
つまり、平易で明快な文章に整えることは、目の前のユーザーへの思いやりであると同時に、海外のユーザーの増加や、AI・検索技術の進化に備えるための「未来への投資」の一面もあるのです。
今日から実践!ユーザーに優しい文章を書く4つのポイント
UXライティングは、特別なスキルが必要なものではありません。ここでは、文章作成に慣れていない方でも取り入れやすい、文章を「やさしく」するための4つのコツをご紹介します。
ポイント1:短く、簡潔に書く
Webサイトを訪れる人は、細かい文章をじっくり読むことはあまりありません。大切なのは、ひと目で要点が伝わること。
一文を短く、構造はシンプルに。伝えたいことが多いときも無理に詰め込まず、一文60文字以内に収まるようにしましょう。箇条書きで簡潔に記載するのも効果的です。
一文を短く、構造はシンプルに。伝えたいことが多いときも無理に詰め込まず、一文60文字以内に収まるようにしましょう。箇条書きで簡潔に記載するのも効果的です。
ポイント2:専門用語を避け、分かりやすい言葉で
社内では当たり前に使っている言葉でも、初めて見る人にとっては意味が伝わらないこともあります。「このサービスは〜という技術を使い…」ではなく、「このサービスなら、〇〇の作業がボタンひとつで完了します」のように、ユーザーがイメージしやすい表現に置き換えましょう。
ポイント3:丁寧すぎず、親しみやすく
「〜していただくことが可能です」など、丁寧すぎる表現は、かえって堅苦しく感じられる上に、文章が長くなり内容がわかりづらくなる原因にもなります。「〜できます」「〜してください」といったシンプルな言い回しの方が、読みやすく、親しみが感じられます。場合によりますが、必要以上に丁寧な表現には注意しましょう。
ポイント4. ネガティブよりポジティブな表現を
注意や制限を伝えるときも、なるべく前向きな言い回しを選びましょう。
【NG例】パスワードが8文字未満では登録できません。
【OK例】パスワードは8文字以上で登録してください。
伝えている内容が同じでも、否定的な表現は読む人に無意識の内にストレスや冷たさを感じさせてしまうことがあります。表現を少し変えるだけで、ユーザーの受ける印象は大きく変わりますので、意識してみてください。
【ウェブサイト文章改善チェックリスト】
文章を作成する際は、以下のチェックリストを活用しながら、自社サイトの文章を見直してみてください。
◾️ 一文が長すぎないか?
・一文が長くても60文字以内に収まるのが理想
・箇条書きなどを使用して情報を簡潔に
◾️ 業界用語・専門用語が多用されていないか?
・箇条書きなどを使用して情報を簡潔に
◾️ 業界用語・専門用語が多用されていないか?
・誰が読んでも理解できる表現が理想
・ユーザーが「自分ごと」として内容をイメージできることが大切
・ユーザーが「自分ごと」として内容をイメージできることが大切
・やむを得ず専門用語を使用する際は、注釈や平易な説明をつける
◾️ユーザーが次に何をすればいいか明確にしめしているか?
・ボタンの文言が「無料で資料請求する」など具体的
・フォームの入力エラーの際、適切にサポートできる注釈を入れる
・フォームの入力エラーの際、適切にサポートできる注釈を入れる
まとめ
この記事では、UXライティングの基本から、ウェブサイト改善に役立つ実践ポイントまでを解説しました。デザインや機能も大切ですが、「わかりやすく伝えること」も、同じくらい重要な要素です。
伝わる文章は、ときにデザインや機能以上の効果を生み出します。サイトの使いやすさを高めるだけでなく、お問い合わせや購入といった成果の向上にも直結します。さらに、AI活用や多言語対応といった将来的な拡張性にも貢献するでしょう。
今回ご紹介したUXライティングの視点を参考に、一度ご自身のウェブサイトの文章を見直してみてくださいね。
何かお困りごとやご相談がありましたらお気軽にご相談ください。